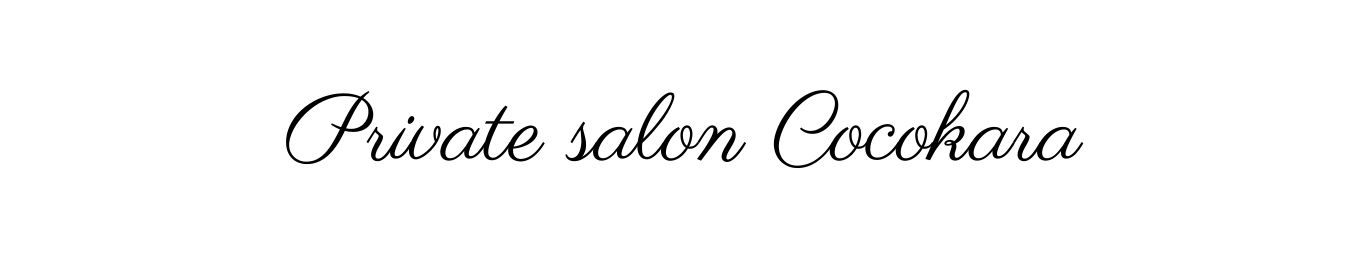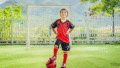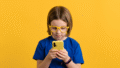SNSが心と脳に与える影響とは?──便利さの裏にある“見えない負担”
■ はじめに
SNSは、いまや私たちの生活の一部です。
友人とつながったり、好きな情報を手軽に手に入れたり、自己表現の場にもなっています。
けれど、その便利さの一方で、
「なんだか疲れる」
「誰かの投稿にモヤモヤする」
「見ないと落ち着かない」
…そんな心の変化を感じたことはありませんか?
SNSは、脳と心に少しずつ影響を与えているツールでもあります。
この記事では、SNSがどのように私たちの心理や脳に作用しているのかを、やさしく解説していきます。
■ SNSは“脳の報酬回路”を刺激する
SNSを使って「いいね!」やコメントをもらったとき、ちょっと嬉しくなりますよね?
それには脳の仕組みが深く関係しています。
私たちの脳には「報酬系」と呼ばれる神経回路があり、うれしいことがあるとドーパミンという快感ホルモンが分泌されます。
SNSで起こるこんな場面は、まさに報酬系が刺激されている瞬間です:
-
投稿に「いいね」がつく
-
フォロワーが増える
-
誰かが返信してくれる
これらが、**ちょっとした“快感のごほうび”**として脳に記憶され、SNSを繰り返し使いたくなるのです。
■ スクロール疲れと情報過多
SNSでは、1分で数十件もの投稿を目にすることがあります。
楽しい動画もあれば、ショッキングなニュース、誰かの自慢や悩みなど…情報はジャンルを問わず次々に流れてきます。
このような状態が続くと、脳は知らず知らずのうちに**「情報疲労」**を起こします。
情報過多による主な影響:
-
集中力の低下
-
記憶力の低下
-
注意散漫になる
-
睡眠の質が下がる
スマホを見たあとに「なんか疲れた」「頭がぼーっとする」と感じるとしたら、脳が疲れているサインかもしれません。
■ SNSが引き起こす心への影響
◎ 比較による自己否定
SNSでは、キラキラした生活や成功体験、美しい写真が数多く投稿されます。
それを見て、「自分はなんてダメなんだろう」と感じた経験、ありませんか?
他人と自分を比較する癖が強くなると、
-
自尊心の低下
-
無力感や劣等感
-
他者承認への依存
が生まれやすくなります。
「SNSの世界」が現実よりも鮮やかに見えることで、自分の今に価値を感じられなくなることもあるのです。
◎ 承認欲求の強化と不安
投稿をして「反応が少ない」と落ち込んだり、フォロワー数を気にして一喜一憂したりするのも、SNSならではの心の動きです。
これは、承認されたいという気持ちが強化されているサイン。
その結果:
-
つねに他人の評価を気にする
-
SNSから離れられない(FOMO:取り残される不安)
-
自分の感情や判断がぶれやすくなる
という心理的負担が積み重なります。
■ SNSとうまくつき合うためのヒント
SNSそのものが「悪いもの」ではありません。
大切なのは、主導権を自分に取り戻すこと。
以下のような意識を持つことで、SNSと健全な距離感を保てます。
① 使う時間を決める
アプリに使用制限をかけたり、「朝と夜は見ない」などルールを設けることで依存を防ぎます。
② フォローする相手を見直す
見ていて疲れる、イライラする投稿はミュートやフォロー解除を。
“心地よさ”を基準に選びましょう。
③ 「見る専門」から一歩引いてみる
情報を得るだけの「受け身」な使い方をやめ、一時的にログアウトしてみるのも効果的。
心が静まって、自分の感覚が戻ってくることもあります。
④ SNS以外で満たす時間を増やす
リアルな人間関係、自然に触れる、趣味に没頭する…。
“今ここ”の体験に集中する時間が、心と脳をリセットしてくれます。
■ おわりに
SNSは、上手に使えば便利で楽しいツールです。
でも、その使い方次第で、心と脳に負担をかけてしまうこともあるのです。
自分の心がざわついていると感じたら、
一度SNSから離れて深呼吸をしてみてください。
「見ないと不安」ではなく、「見なくても大丈夫」と思える心の余白を、少しずつ取り戻しましょう。
あなたの心と脳を守るのは、あなた自身の選択です。
SNSに振り回されず、自分のペースで心地よく暮らしていくために、
今の使い方を見直してみることから始めてみませんか?